|
カバーコラム
毎月「暗渠」「ステビア」「農業」「農村景観」をテーマにカバーコラムを書いて
 ■優益暗渠排水協会 ■優益暗渠排水協会
四国の牟礼で全国の土管メーカーが集まるとの事で1時間程暗渠排水の話をさせてもらいました。
ほとんどの人が電話で話をした事がありましたが、実は初対面でとても不思議な感覚。
皆意識が高く勉強熱心な社長さん達でした。
写真はφ60mm L=600mmの土管を製造しているところです。
縦抜きでソケットの形状が同時に形成されます。
牟礼はイサムノグチのアトリエのある地域で、前職の時に一度訪れた事がありました。
次の日はアトリエを訪れ、干ばつで取水制限の出ている時期でしたが、彫刻が洗われるかのようなめぐみの雨で、また、雨の庭園も気持ちの良いものでした。
偶然にも瀬戸内国際芸術祭が開催されており、丹下健三の展覧会だけ見て来ました。
イサムノグチと丹下健三は交流のあった仲ですが、二人を引き合わせたのは「猪熊玄一郎」だとの事です。
香川県庁を丹下健三が設計したきっかけも猪熊玄一郎が紹介したようです。
牟礼には今も有名な彫刻家「流政之」さんがいますが、直島や瀬戸内の芸術が盛んになる原点は猪熊玄一郎が香川にいたからでは無いかと思います。
公共建築にデザイン性の高い物が建ち、県知事と直島の町長の意識が高く、日本を代表する建築家、企業、デザイナーが香川を訪れるようになり、今の瀬戸内になったようです。
高松は半世紀も前にアートディレクターの役割を果たした人物が居たのだと!
もう一度Landscapeの観点から牟礼を瀬戸内を訪れてみたいと思いました。
2013年8月
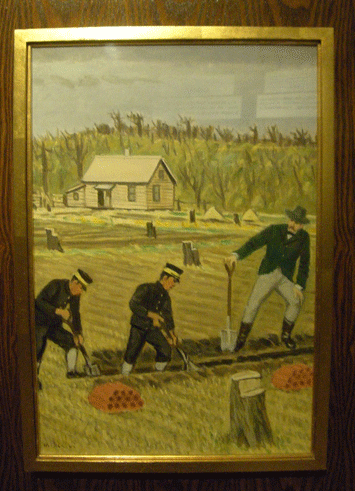 ■エドウィン・ダン ■エドウィン・ダン
江別で暗渠排水の歴史を少し調べました。
「屯田兵時代に徴兵の終わった人間が、その知で農業者として生きて行く為にはどうしたら良いか」時の開拓次官黒田清隆は、クラーク博士やエドウィンダンに相談していました。
ダンの指導は、 1プラウをかける。 2輪作する。 3瓦筒を埋める。
との事でした。
ここで出てくる「瓦筒」とは「土管」の事です。実際には「tile drainage」と説明したようです。
エドウィンダンは江別の農業の基礎を作った人で覆いに讃えられるべきである。とも書いてありました。
写真はエドウィンダン記念館に飾られている土管暗渠を指導しているダンの様子です。
江別市史によると施工されたのは明治13年、日本ではじめての土管暗渠と書かれています。
おそらく札幌農学校から土管を船に積んで石狩川を渡って江別に来たのうだろうと思われます。
2013年7月
|
