 ■はじめの地下灌漑
■はじめの地下灌漑
久しぶりに会社の書庫をあさっていたら面白そうな
報告書を発見した。
写真では見づらいが昭和50年3月に新潟県農業試験
場から報告された「浅暗渠の多目的利用に関する試験
成績書」なるものだ。
読んでみるとこれは「地下灌漑」の考え方だ。こ
こで言う「多目的利用」とは「転作」の事であり、も
う一つの目的として「水資源の節約、有効利用」であ
る。
今でこそ「地球温暖化」が叫ばれ「水の確保」が問題になって来ているが、この
時代にここまで視野に入れた研究がされていた事は驚くばかりである。
簡単に説明するとほ場に「深い暗渠」と「浅い暗渠」を入れ、これが「水を排出
する暗渠」と「水を供給する暗渠」の役目をし、「浅い暗渠」をパイプラインと繋
げ「深い暗渠」の流末に排水桝を設置しこの桝で地下水位を調整する工法である。
この時代に暗渠とパイプラインを繋げる発想がすでにあったのがすごいし、排水桝
で水位を調整する方法はサッカーグランドで使われているのと同じである。
以前つとめていた事務所の所長に「太陽の下で新しいデザインは出ない」と言わ
れた事がある。つまり「人間の永い歴史の中でまったく新しい形が出る事は無い」
という事であり、まあ、「デザインの歴史を勉強すれ」と言われたのである。
暗渠排水も同じであった。
私は「地下灌漑」がこれからの農業に必要だと強く思っているが、何も新しい工
法では無かったんだと実感させられてしまった。
2007年12月
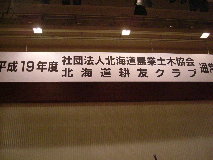 ■北海道農業土木協会奨励賞
■北海道農業土木協会奨励賞
8月31日に「北海道農業土木協会」で有
材心破が奨励賞を受賞しました。
このような団体があるのは知っていました
が、技術評価活動をしていたのは知らず、
過去の受賞内容を拝見すると立派な研究が
たくさんあり、その中の一つに選ばれたこ
とはとても光栄なことだと思いました。
表彰会場には大学時代の教授がおり、お目にかかるのは卒業以来で、優秀な生
徒ではなかったので、先生は覚えていらっしゃらなかったが、色々と話ができてよ
かったです。
会場には他にも今後の北海道の農業土木に必要なキーマンが居たように思え、そ
のような人たちと出会えたことはとても私にとってとてもありがたい事だと思いま
した。
このような賞を受賞でき、多くの方に出会えたのも、一緒に受賞した久保田さん
をはじめ、多くの方に支えられたからだと思います。
また、機械開発に関わった我が社のスタッフの技術力のおかげだとも思っていま
す。
今後も、既成概念にとらわれる事なく、新しい発想から日本の農業のために努力し
なくてはと思っています。
2007年9月
 ■世界一贅沢な運動会
■世界一贅沢な運動会
以前公園の設計をしていた時期がある。
この「アルテピアッツア」は私が思うに北
海道で一番良い公園だ。
仕事で疲れたときにここに来て「心の洗
濯」をする。彫刻がまるで木々のように自
然とその大地からはえてきたように置いて
ある。川のせせらぎや木々の葉が揺れる音等、ここに居ると強く自然を感じられる
場所だ。
その公園の一角に幼稚園がある。幸運な事に私の「甥」がここの幼稚園に通っ
ている。毎年この幼稚園の運動会に来ることが楽しみである。
子供たちは彫刻の間を走りぬけ、父兄は彫刻の上に座り子供たちを応援し、もち
ろんその上でお弁当を食べる。
彫刻が自然とそこにあり、主張せず、しかし、しっかりと存在している。
幼稚園の中の廊下に彫刻が置いてあり、子供たちはそれを当たり前の物として受
け入れている。
こんな環境で育った子供はどれだけ幸せであろう。
子供たちは何も気づかづに生活している。自然である。
今年で「甥」が卒園するので最後の「世界一贅沢な運動会」を満喫した。
2007年8月
 ■ものづくりテクノフェア
■ものづくりテクノフェア
先日北洋銀行主催の「ものづくりテクノ
フェア」に出展いたしました
「世界農業の状況」から「日本農業の状
況」そして、我社が行っている「暗渠排
水」「ステビア資材」がどのような役割を
果たすのかを説明するパネルを作りました。
世界的農業事情としては、「途上国の人口増加」「中国人の食文化の変化」そ
して「バイオエネルギーの拡大」
日本国内の状況としては「先進国と比較しての農地面積の少なさ」「海外に依存
している農地面積の広さ」「農水省が発表している不測の事態の対応策」
圧倒的農地面積の不利をどのような技術を持って解決していくのかがナラ工業の
使命と強く感じています。
展示会はとても好評で多くの方に見ていただきました。意外だったのは「ステビ
ア」が天然甘味料だと知らない人がたくさんいた事です。葉っぱをちぎって食べて
いただき、皆さんあまりの甘さに驚いていました。
多くの企業の方が来ましたが、業種を広げるために興味を持っていただいた企業
が多かったようです。 日本は「いざなぎ景気」を抜いたと言っていますが、北海
道経済はまだまだで、多くの企業が努力をしていることをつくづく感じました。
来場していただいた企業の方々ありがとうございました。
2007年7月
 ■線から面
■線から面
7cmの有材心破工法を行ってから、「地
下灌漑と併用するともっと効果が上がるの
ではないだろうか」と考えるようになっ
た。地下灌漑で土壌水分をコントロールで
きるようになったが、あくまでも暗渠管の
直上にはすぐに反応するが渠線間ではうま
くコントロールが出来ないであろう。有材心破と組み合わせる事によりほ場の土壌
水分を「線的管理」から「面的管理」に出来るはずだと思って色々な所に話をして
みた。
やはり同じような考えを持つ人が居る者で「粘土地における地下灌漑の効果」を調
査している人がいた。
「水を透しやすい泥炭地ではコントロールしやすく、作の出来がほぼ一定だが、粘
土地では渠線間に水が行かなく、作の出来にムラがあり、これでは地下灌漑を設備
した効果が出てこない」と話していた。
そこで、今年その試験ほ場に有材心破工法を施工させてもらった。今年で3年目の
調査だがほ場全面に水が行き渡っているとの事である。
今迄の調査では、暗渠直上から4m離れると収穫量が落ちると言う結果が出ている
ようだが、今後の調査が楽しみである。
ほ場内の収穫量にムラが無くなり、日本の限られた農地の中での収量が少しでも上
がれば自給率の向上に役立つであろう。
2007年6月
 ■ピンネシリ岳
■ピンネシリ岳
先日無材暗渠の実演会を開いた。
春の北海道は山に残雪があり、空は青く
とても美しい風景である。この風景を見な
がら仕事が出来る事はとても贅沢だと思っ
た。通りがかりの車から見ている人は我々
の仕事が農作業風景として見られているは
ずだ、自分たちが風景になった瞬間だと思う。 これから本格的に農作業が始ま
る、徐々にピンネの山の残雪も無くなっていき本格的に春を感じる時期だ。
無材暗渠の方は見学に来ていただいた農家さんが驚く程効果があった。掘った本
人が驚く程の効果だったからあたりまえだ。
今迄実績の無い地域の農作業の役に立てるよう願い、また、ピンネシリの麓に来れ
る事を願う。
2007年5月
 ■疎水材
■疎水材
先日久しぶりに上湧別にある会社を訪れた。ここに
は熱心な方がおり、暗渠排水のモデルを作り、暗渠排
水の研究をされている。
最近、疎水材の効果の問い合わせが続いているので、
意見交換をさせてもらった。
根室や天塩では暗渠排水から流れる水が、漁業に悪影
響を与えていないか研究している。
石川県でも「瓦チップ」を疎水材に使用し初めてい
るが水質浄化の効果はまだ調査されていなかったが、
河北潟にある農家さんが「河北潟は今、水質浄化が必要であるから、自分の所から
流れる水はきれいな水を流したい!」との事で「瓦チップ」を使い、独自に水質調
査を始めるらしい。(このような熱心な農家さんに出会えた事に感謝したい気分で
ある。)
施工する立場としてまだまだこの疎水材の効果の研究が必要であろう。我社のよ
うな小さな会社だけで出来る事には限界があるが、少しずつでもいいから上湧別の
会社のようにやらなくてはならないだろう。(随時HPで公開して行きます。)
2007年4月
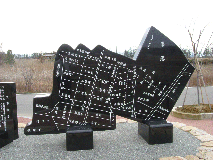 ■場所の記憶 場所の愛称
■場所の記憶 場所の愛称
私たちの行っている「ほ場整備」は農業
の「生産性向上」「効率化」のために小さ
なほ場を大きなほ場にしている工事であ
る。
これはある意味「モダニズムデザイン」で
あると思う。
モダニズムデザインは誤解を恐れずに私の解釈を述べると、単純な簡単な形でより
豊かな表現を 追求する事だと思う。このほ場整備も「単純な形を作り農家さんが
豊かになる」と考えると同じかもしれない。(機会があればHPで農村風景とモダニ
ズムデザインの共通性を述べたい。) しかし、小さな農地の形にも意味がある
物である。川や地質などの地形条件からほ場の形が決まったりした物である。
写真は「ほ場整備」を完成した時に作られる「記念碑」の裏面である。 この地
域には農道などに「愛称」のような名前が付いていたのである。しかし、ほ場整備
に伴い形が大きく変わり、その「愛称」も呼ばれなくなり忘れ去られようとしてい
たので、記念碑の形を地域の形にし、昔からの「愛称」を刻んだのである。
農村景観を扱う者としては、このような心遣いを持った人が農業土木分野にも居
る事をうれしく思う。この地域の歴史は子供達にも受け継がれて行く事を願うばか
りである。
2007年3月
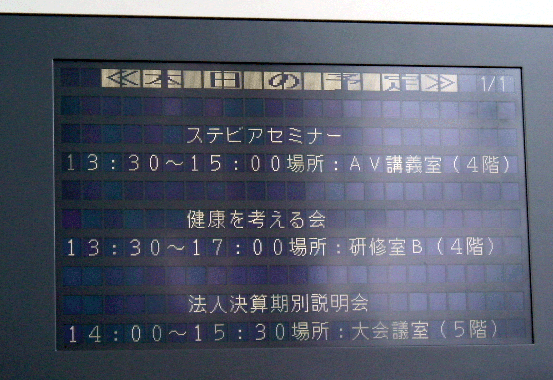 ■花咲かじいさん
■花咲かじいさん
先日たて続けに農業の集まりに参加し
た。 どちらの集まりも農業に熱意を持つ
人がたくさん集まった。
石川県ではステビアセミナーにアドバイ
ザーとして参加した。 石川県は伝統文化
に育まれている「加賀野菜」の産地であ
る。 そんな地域でも伝統に胡座をかく事なく新たな切り口を開こうと努力をして
いる。
次の日に北海道で「未来農場」を描く集まりに参加した。 私の農業の価値に対
する思いも話せた。 2時間という長い時間熱い討論が繰り広げられ、とても充実し
た時間を過ごせた。
両方の集まりで感じた事は、農業の未来は自分たちの足下にあるように思えた。
ステビアセミナーでは、参加者がまるでステビアが「魔法のハーブ」のように思わ
れていたが、一緒にアドバイザーとして参加した京都でステビアを利用している農
家さんが「自分の求める農業のどの位置にステビアを利用するのか皆さんが自分た
ちで考えなくてはならない」と話していた。京野菜を作っている農家さんの凛とし
た姿勢を感じた。
隣の人がうまく行ったからそれをそのまま鵜呑みにしてはだめだと思う。 そ
う、まるで「花咲かじいさんの隣のいじわるじいさん」になっては行けないのだ。
そう考えたら「花咲かじいさん」のお話は私たちに物事に対する姿勢を伝えている
のかも知れない。
2007年2月
 ■部分と全体
■部分と全体
写真は先日知人から送られて来た「酒器」である。
私はこれを見て久しぶりに「部分と全体」と言う事を
思い起こされた。
知人は「さかずき」を作る仕事に関わっているが、こ
の商品開発のプロデュースをしたらしい、これは単な
る商品ではなく「酒文化」の提供だ。「酒」「器」と
単体で考えるのでなく、部分の集合で全体を提案して
いる。 酒の瓶をベネチアングラスでおしゃれに作っている酒蔵もあるが、それは
あくまでも単体の努力で、全体の領域には達していない。
この提案の仕方は「まちづくり」でも「暗渠排水」でも忘れてはいけない視線だと
思う。 まさにランドスケープである。土木、建築、と単体の集合から「まち」は
出来ているが、それを包括して考える事が大事である。私の住む町も「やきものの
町」と言われているが、これを文化の域までに押し上げて行かなくてはならない、
その時に単体で考えるのではなく、地元農業と器を融合させ新たな食文化としてな
くてはならない。
暗渠排水もステビアも単体では文化には成り得ないが、文化の一部として使命を全
うする必要はあるだろう。
2007年1月
