|
カバーコラム
毎月「暗渠」「ステビア」「農業」「農村景観」をテーマにカバーコラムを書いて行きます。
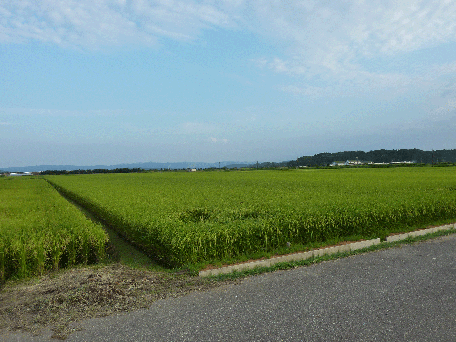 ■リハビリ暗渠 ■リハビリ暗渠
8月の末に打合せで石川県に行った。
石川県七尾市の中島地区は海抜が低く塩
害の考えられる地域である。
石川大学の先生の考えのもと暗渠排水の
復活の方法を模索している。
先生は地球温暖化の為日本でも中東のよ
うな塩害が起きる可能性があると考えられているようで、その為には、現在の暗渠
を利用してより効果がでる工法が求められる。一様、私が網走で行った工法の資料
を提出した。宮城県では「モミタス」という機械で疎水材の入れ替えを行ってい
る。
総じて、世の中の流れとして、暗渠排水の再利用が大きな流れのようだ。
久しぶりに夏の石川県を訪れたが、やはり暑い!
2009年9月
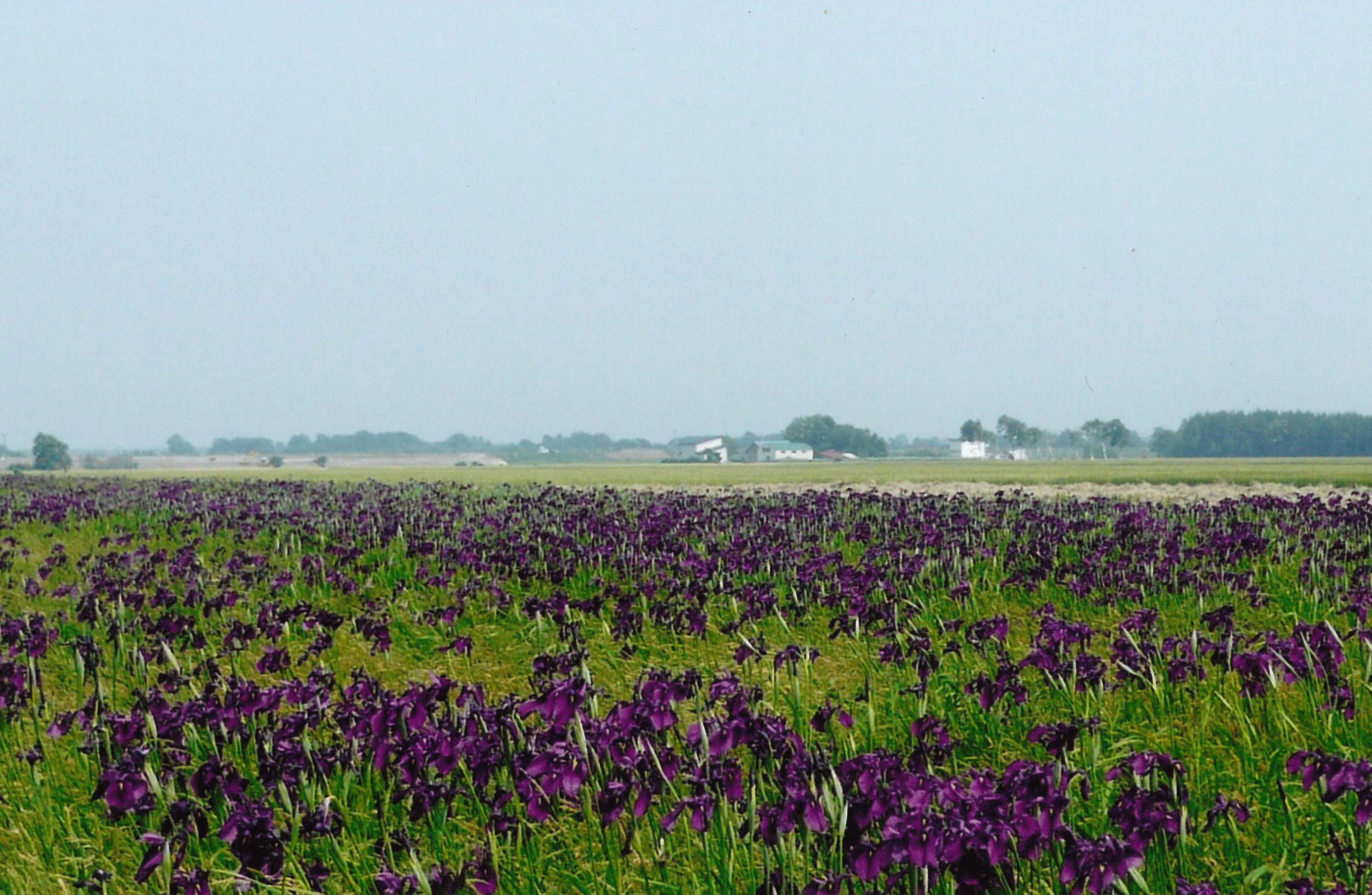 ■ノハナショウブの郷 ■ノハナショウブの郷
江別に花菖蒲の自生する場所がある。
実は知人の酪農家さんの水はけの悪い牧
草地でほとんど管理していない状態らし
く、農家としては恥ずかしい話なんだっと
言っていましたが、これはこの地域の財産
だと思った。
自然と歴史は地域づくりでとても大事なテーマになりうる。
この価値に気づいた地域の人が守り始めている。是非このノハナショウブが地域
づくり、地域ブランドのきっかけになって欲しい、「ノハナショウブの咲く郷の農
産物」「ノハナショウブの咲くきれいな水の地域」可能性はあると思う。
私の仕事の主体は「水はけの悪い農地の乾田化」だが、乾田化の技術はそのまま
湿田化の技術とも言える。
生産の為の農地と自然を残す為の農地の調和がこれからは大切だ、新しい農業環
境のあり方をこの地域から提案したい。
ちなみにノハナショウブは園芸の花菖蒲の原種で貴重な花らしい。
2009年8月
 ■セラミック補助暗渠 ■セラミック補助暗渠
春に土管暗渠を行った農家さんのほ場で
セラミックだけの暗渠を行った。
セラミッックは70%ケイ酸分を含んで
いて、牧草にも良い効果をもたらすだろう
との事で行いました。
土管であれば根が深く伸びないとケイ酸
の効果は期待できないが、疎水材として使用する事で早いうちから効果が期待でき
ると思う。
また、左上の写真でも分かるように泥炭の激しいほ場の為、掘削と同時に水が吹
き出し、管を居れなくても一定量の排水の効果はでた。
今の経済情勢上、いかにコストを抑えて排水効果と収量効果の高い暗渠を提案す
る事が、今後の大事なテーマとなるだろう。
二番牧草の生育か楽しみだ。
2009年7月
 ■お祭りのルーツ ■お祭りのルーツ
先日知人の農家さんの田植えを手伝いに
行き、その切り上げに参加した。
昔の「田植え」は地域の農家さんが協力
し合い、順番に地域の田んぼに「田植え」
をし、終わってから「ご苦労さん会」を開
き、お互いの「労」をねぎらったもので、
その「労」をねぎらうのは今も変わっていない。
昔は、その「労をねぎらう会」が「豊作を願う会」になり「お祭り」になったの
だと思う。
春のお祭り、秋のお祭り、共に「豊作を願うお祭り」「豊作に感謝するお祭
り」。
今でも地域ごとに「歌」や「踊り」があり、それが文化になり、特徴ある豊かな
地域が形成されたのだと思う。
今、日本に欠けているのは、この「地域性」で、「まちづくり」でも歴史を大切
にするのは、「地域性」を出すためだと思う。
まさに、日本の国の「地域性」「文化」は農業から生まれたのだと思う。
「巴農場」で新しい祭りを作ろう!
2009年6月
 ■エネルギー変換装置 ■エネルギー変換装置
先日知人の農家さんの田植えを手伝いに
行ってきた。田植えは8年ぶりかな。勿
論、手で植えるわけではなく機械で、この
田植機を見るたびに「この機械ってすげ
〜」って思わされる。誰がこんな機械考え
だしたんだろう。暗渠の土管を配管する機
械をこの発想で作れない物だろうか。
久しぶりにこのような空間に一日、何か幸福感というか癒された感じがした。私
たち人類はこのような作業を2000年以上行っていたのだろう。きっと私の血の記憶
にも、DNAにも刻まれていて、だからこのような風景を見て安心するのだろう。
一緒に働いていた女性の人も「これだけ苦労して植えるのだからお米を大切にし
ようと思う。」と話していた、それが「食育」だと思う。
私たちはどんな人も「食べる」事でしかエネルギーの供給はできない。食べる物
は「草食」「肉食」とあるが、「肉食」も「草食」で始めて成立する。「草食」は
どのように成立するかと言うと「土」と「水」と「太陽エネルギー」である。
そう考えると「畑」「水田」は私たちにとって「エネルギー変換装置」と言える。
最近「eco」が大きく騒がれてきて、「ソーラーパネル」や「地熱エネルギー」や
様々な「エネルギー変換装置」が開発されてきているが、我々は2000年以上前から
大きなエネルギー変換装置を作ってきているのである。水田の形ってどこかソー
ラーパネルに似ている気もするが・・・
ここの農家さんは江別にある「巴農場」で、若者とエネルギッシュな奥さんと技
術に裏付けされた旦那さん達で作られた農業法人で、我が社のHPでも商品を扱って
いるが、最近HPを立ち上げたようだ!
2009年5月
 ■ソケット付き土管 ■ソケット付き土管
北海道ではめずらしい「ソケット付き土
管」の施工を行いました。
この酪農家さんは「土づくり」に熱心な
方で、それには「土」で出来た土管が大事
だと言っています。
しかし、この牧草地の土壌は泥炭地と言う
特殊な土壌で北海道の従来の土管では不当沈下が起き、永続性が期待できません。
そこで特注でこの土管を作っていただきました。
私の仕事はただ管を埋設する仕事ですが、農家さんが何を求めて暗渠排水を行う
のか深く知りたく、農家さんと「土づくり」や「農業」の話を聞きます。その上で
どのような方法が良いか提案しているつもりです。
「この土が牧草を育て、その牧草を牛が食べミルクを出し、そのミルクを私たち
が飲み、私たちは間接的に「土」を食べているのと同じで、だから「土づくり」が
一番大切なんだよ」と話され、また「私の牛のミルクが1リットル多くとれる事
で、外国の貧しい人の口に入る可能性が増えるかもしれない」と話されていて、私
はこの酪農家さんの姿勢にただ驚くばかりでした。
農業の奥の深さ、物を作る姿勢を教わったように思えます。
私の仕事が少しでも農家さんの役に立つ事を願って仕事をしていますが、このよ
うな農家さんに出会える事を楽しみにしてい仕事をしているのかも知れません。
2009年4月
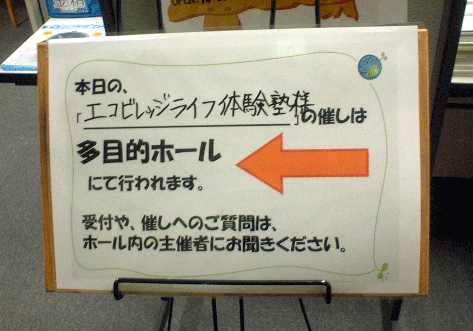 ■エコビレッジ ■エコビレッジ
先日知人の講演する「エコビレッジ」の
話を聞きに行った。
設計事務所時代にお世話になった人であ
る。2年間ヨーロッパの「エコビレッジ」
で生活していたそうだ。
昔、よく「コーポラティブ住宅」と言う名前を聞いたが最近は聞かなくなった。
エコビレッジとは、コーポラティブ住宅の「村」バージョンだと思った。
食糧やエネルギーの自給自足をはじめ「住まい方」の問題なんだと。
カバーコラムの最初の頃に「五箇山の世界遺産」の話を書いたが、昔の「五箇
山」はまさにエコビレッジだったのだと思う。
知人は北海道で「北のエコビレッジ」を作ろうとしていて、私も有機農業や農村
風景計画など積極的に協力しようと思っている。
有機農研究会のメンバーにも声をかけようと思う。
北海道から新しい農村のスタイルが発信できる事を目指したい。
2009年3月
 ■ステビアを利用した土づくり勉強会 ■ステビアを利用した土づくり勉強会
2月25日に江別で「土づくり勉強会」を開
催しました。
38名の方に参加してもらい、遠く石川県や
帯広市から参加した方もいました。本当に
ありがとうございます。
講師に昔から指導いただいている先生におこしいただき、「作物は土を食べて育
つ」と言う話から、今のほ場の土は肥料を吸わす媒体に過ぎず、作物の根が伸びる
状態に無いと言う事を話していただきました。
その為にはまずほ場を乾かす事が必要で暗渠排水が基本である。
そして、土づくりには、微生物の活動と大きな関係があり、今の無機質肥料を直接
植物に吸わせる農法では、微生物の活動する場がなく、本来は有機質肥料を投与し
時間をかけて植物に吸われる状態に変化させる事が大切であり、ステビアはその過
程を助けるものであるとの話でした。
2009年2月
 ■セラミックソイルとN・ステビア ■セラミックソイルとN・ステビア
土づくりを研究して行くと土壌菌の事に行
き着く。ステビアは好気性微生物の活動を
活発にすると言われているので、土にN・ス
テビアとセラミックソイルを混ぜてみた。
1ヵ月程で白カビが発生し2ヵ月後にはホ
クホクの土が出来た。
ステビアを畑に播く事は少なくとも土壌内でこのような微生物の活動が起きている
事が証明された。
ステビアを入れる前と後での土壌分析を行った結果ほとんどの数値が上昇した。
(上昇しすぎる程であった)
土づくりと微生物の活動は大きな関係があり、今の農業の無機質肥料の農法で
は、微生物の活動する場がなく、植物が直接肥料を吸ってしまうが、本来は有機質
肥料を投与し時間をかけて植物に吸われる状態に変化させる事が大切だ、ステビア
はその過程を助けるものである。
2009年1月
|
