|
カバーコラム
毎月「暗渠」「ステビア」「農業」「農村景観」をテーマにカバーコラムを書いて行きます。
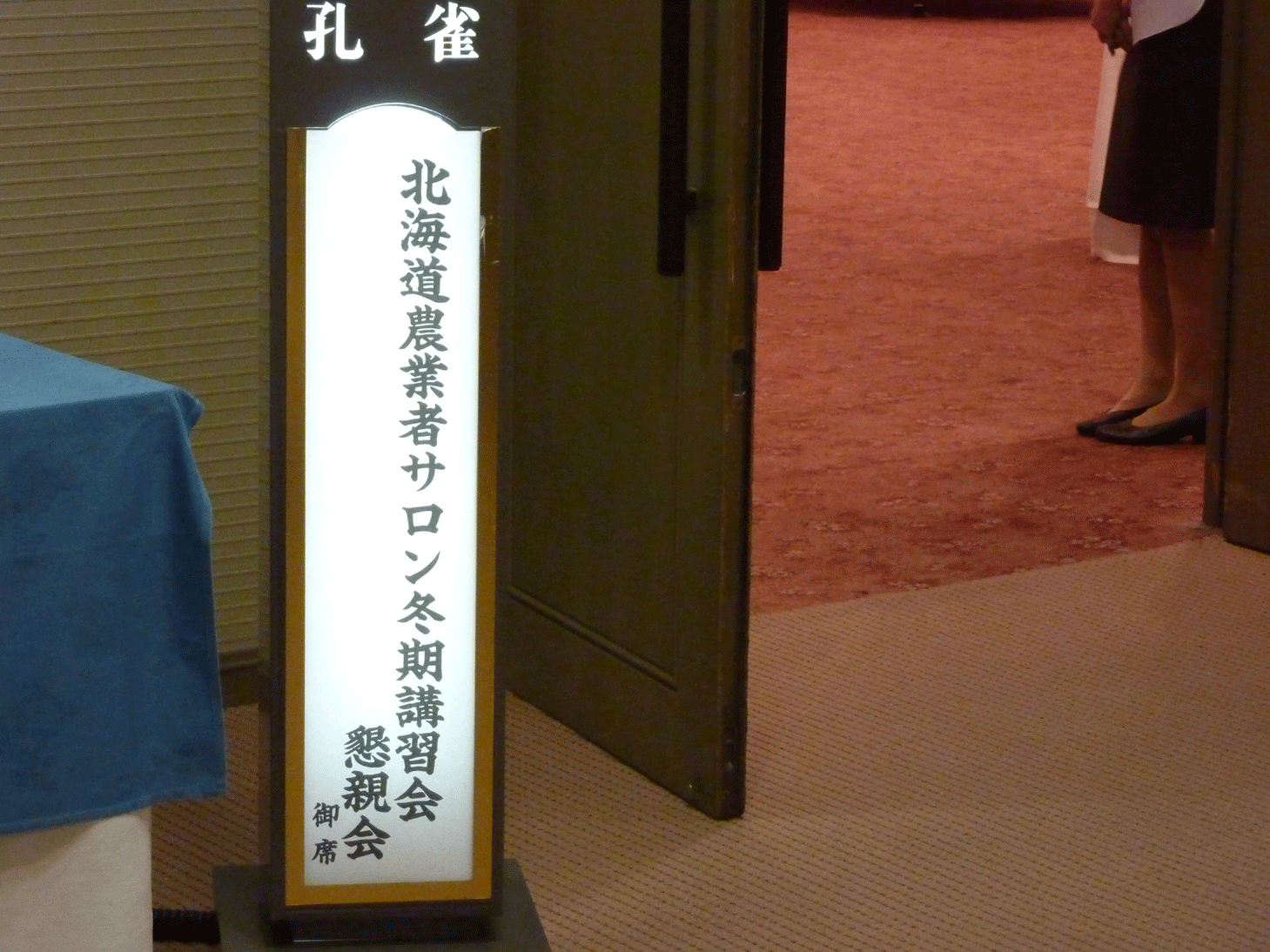 ■農業者サロン1 ■農業者サロン1
先日北海道農業者サロンに参加してきました。
かれこれ三回目の参加ですが、刺激的な人の集まりだ。
「月のみちかげと木の中に居る虫の関係」「インドの経済成長の理由」「共生木」「アミノ酸、ケイ酸」
話が多岐に渡り付いていくので精一杯って感じだったが、自分の考えを持てるもの、そんな考え方があったのかと驚くもの、早速実践してみたいと感じた。
冬の間にアイディアを整理し、自分の役割を考え農家さんに提案したいと思う。
2010年11月
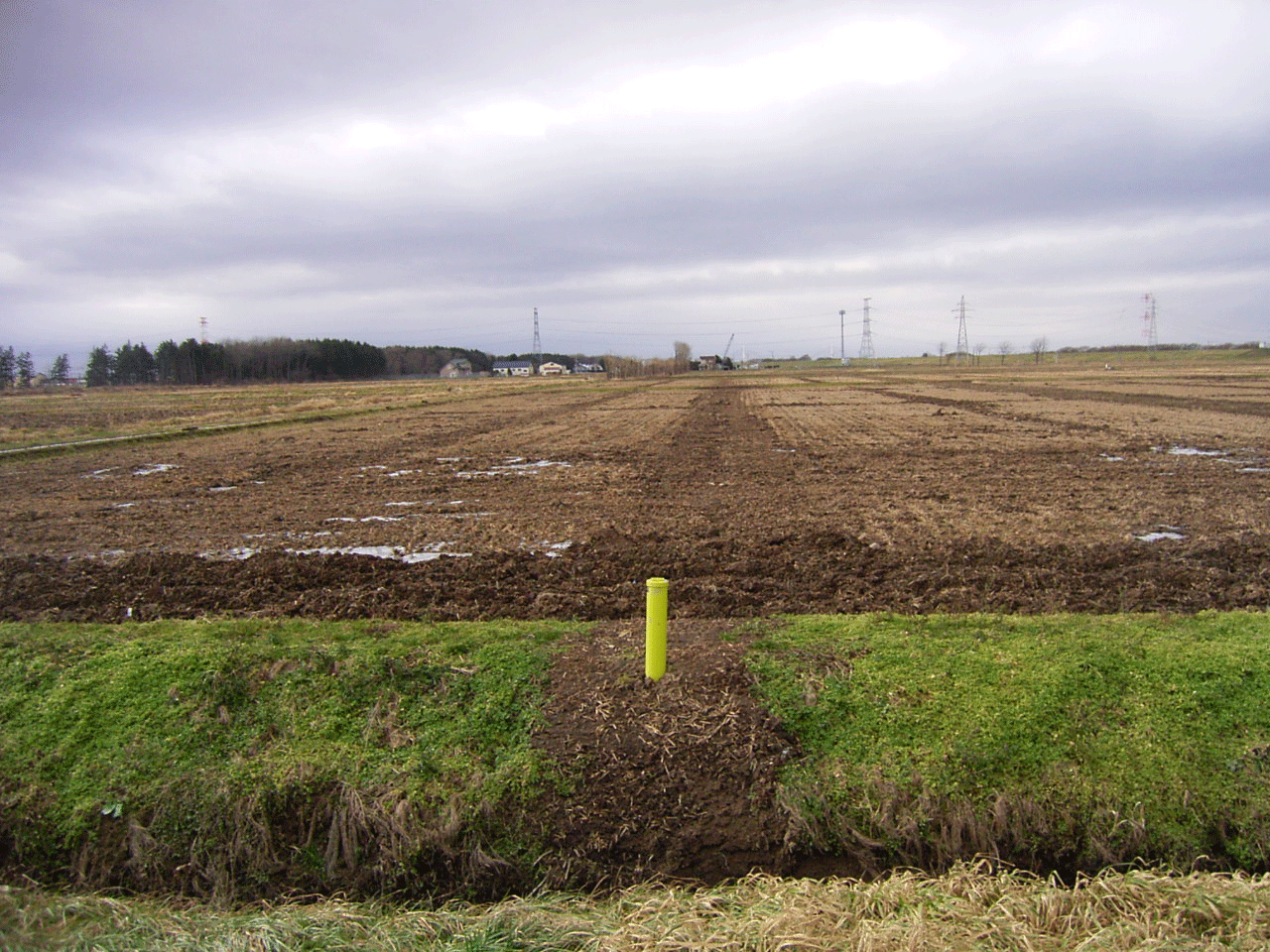 ■低コスト暗渠 ■低コスト暗渠
低コスト暗渠を提案しました。真ん中で黄色く見えるのが「水閘」で、水田の水を貯めたり、抜いたりします。
その水閘から写真奥にまっすぐに見える土の色の違う場所が、暗渠を施工した跡です。
それを交差するように見える跡と両サイドに写真奥に見える跡が「無材暗渠」の跡です。
この水田では、材料を使った暗渠は真ん中の1渠線だけです。本来の暗渠の1/3程度のコストです。
来年の農業成果が楽しみです。
2010年10月
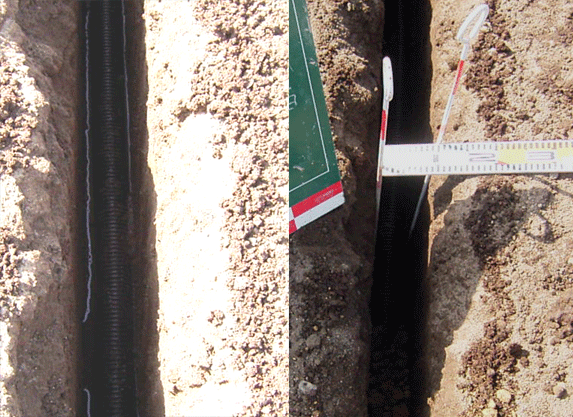 ■掘削幅10cm ■掘削幅10cm
我が社のHPでも紹介していますが、掘削幅と排水量の明確な差は無いと言われています。(北海道農業中央試験場調べ)
そこで、疎水材の量を少なくし、コストを抑えた暗渠排水が出来ないか考え、10cmの掘削幅で6cmの管を埋設する暗渠を行いました。
このような暗渠の設計指針は日本中どこにも無く、農家さんの理解を得て施工しました。
農家さんも硬盤を壊して水が下に行けば掘削の幅は関係ないと考えていたので可能でした。
施工費は従来の暗渠より2割程度安くなりました。
暗渠専門会社として、農家さんが何を求めているのか理解し、低コストで農家さんの為になる工法を考えなくてはなりません。
2010年9月
 ■ORAC(オーラック) ■ORAC(オーラック)
みなさん、ORAC(オーラック)という言葉をご存知でしょうか?
よく「ポリフェノール」などの「アンチエイジング効果」とか「抗酸化作用効果」の言葉は聞いた事があると思います。
ORACとは、食品などに含まれる種々の抗酸化物質(カテキン、フラボノイド、ビタミンEなど)の抗酸化能力(機能性)を分析する方法であります。
N・ステビアで調べた結果「500μmole TE/g」ありました。この数値はブルーベリーの5倍以上です。
それでは、ステビア農法の農作物はどれくらいかと思い、写真にある鈴木農園さん(江別西インターそば)のトマトを調べました。
普通トマトは「3.6μmole TE/g」程度ですが、ここのトマトは「5μmole TE/g」ミニトマトに関しては「12μmole TE/g」計測できました。
これからは「価格」「おいしさ」プラス「ORAC値」を気にしながら食品を買う必要があるのでは?
健康な作物は健康な土づくりから始まります。
ちなみにアトリエ陶の食祭で鈴木さんの野菜が食べれます。
2010年8月
  ■オホーツクセラミックチップ&トレンチャー ■オホーツクセラミックチップ&トレンチャー
先日、網走管内でトレンチャー掘削の有材心破でセラミックチップの施工を行いました。
上湧別の土管屋さんが試験的にセラミックチップを作成してくれました。
以前、北海道で施工した時には、名古屋からセラミックチップを運びましたが、「北海道でも生産出来ないか」との思いに応えてくれました。
事業に採用されるには、まだまだハードルがあると思いますが、「水質浄化」や「ケイ酸補給」等と色々研究してみても「物」が無い事には「絵に描いた餅」に過ぎませんでした。
北海道での最初の一歩ですが、将来大きな一歩になるよう協力したいと思っています。
オホーツクの暗渠排水は「バックホウ掘削」が主流ですが、「低コスト」で尚かつ「高効果」な暗渠を実現するには、「セラミックチップ」と「トレンチャー掘削」はセットで考えていかなくてはならないと思います。
多くの農家さんに理解してもらえるよう、情報を発信していかなくてはならないと思っています。
2010年7月
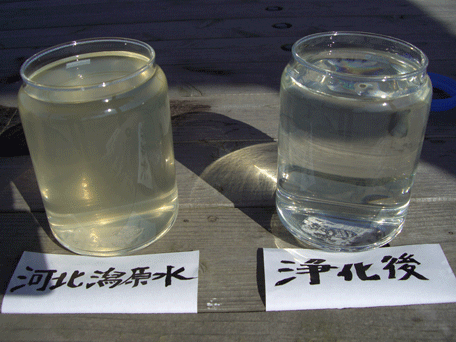 ■水質浄化暗渠 ■水質浄化暗渠
平成14年から石川県でセラミックチップを使った暗渠を施工している。
佐賀県等でセラミックを利用した水質浄化の研究が行われていたので、石川県でもと思っていたら、セラミックチップを利用した水質浄化の実験に参加する機会をいただいた。
石川県にある河北潟という干拓地で、この潟の水質浄化のために、「セラミックチップ」「竹チップ」「珪藻土」の3種類の層をもうけ、そこを流れる水路をつくり、1年前より実験が始まり、一定の効果が実証された。
セラミックチップはあくまでも「浄化」というよりは「濾過」に近いのかもしれないが、「竹チップ」はアミノ酸が豊富にあり、水棲微生物の餌になり、活動の活性化を促しているだろう。
「セラミックチップ」おそらく微生物の安定した住処になっているだろう。
石川県の暗渠排水では「セラミックチップ」か「砕石」と「籾殻」の2層の断面構成が多いが、今後は「セラミックチップ」と「竹チップ」の断面が理想だろうと考える。
瓦や竹の処理に困っている地域があると思うし、河川の水質改善を望んでいる地域も多いと思う。
暗渠排水を行う事で、一石二鳥にも三鳥にもなる事をもっと伝えていかなくてはならないと感じた。
2010年6月
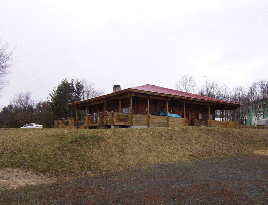 ■日本最北 ■日本最北
北海道農業土木協会で表彰された有材心破工法が訓子府で採用され、久しぶりにトレンチャーに乗る日々を過ごしました。本当であれば有材心破工法の紹介をするべきなのでしょうが、自分が運転していたので写真が撮れませんでした。またの機会に・・・
訓子府町は美瑛にも負けない丘陵地のとてもlandscapeのうつくしい町でしたが、町の中心地は住んでいる人を感じられない、いかにも「街路事業で作られた街」って感じで少し残念でした。
しかし、その街なかでも、廃線になった駅舎を改装して、地域の農産物を提供する、住民のがんばりを感じるお店があり、昔「田んぼからのまちづくり」を提案していた人間にとっては自然と足が向きました。
そのお店のメニューで地域の有機農家が提供する「ハーブティー」があり、その中に「さびない人へ」ってネーミングのティーがあり「なんじゃこれは!」って手に取ってみると「ステビア」と書いてあるではないですか!
ステビアは有機栽培でも可能ですが、パラグアイの植物を北見地区で育てている人がいるのに驚きました。
後日、現場が終わってから、この有機農家さんの農場を訪れ、話を聞いて来ました。
HPで紹介する許可をもらって来なかったので、名前は紹介できませんが、とても奇麗な農場でしたので農場の一部の写真を掲載します。(これでもまずいかな?分かる人は分かるね)。
やはりステビアの越冬には相当苦労しているようでした。当社のようにステビアだけを扱っているわけではないので、ステビアを増やそうとは考えていなく、維持できるように努力しているようでした。
北海道にもステビアを栽培している人が居てうれしくなり、たぶん日本最北のステビア栽培農家さんでしょう!
2010年5月
 ■エネルギー変換装置 ■エネルギー変換装置
先日、設計事務所時代の仲間が、「下川町21世紀環境共生型モデル住宅の設計者選定公募型プロポーザル」で最優秀賞を受賞し、竣工の報告会が開かれた。下川町には設計事務所時代の知人もおり、彼にも会いたく、猛吹雪の中車を走らせた。
北大の荒谷先生の自然エネルギー利用の話はおもしろかった。自然エネルギー利用というとすぐに「電気に変える」って発想だが小さな気温差を利用したりして、そのエネルギーを農業に活かそうとしている話であった。これは模倣が必要だな!
これは微気候の考え方だ!
設計事務所時代、休憩施設に微気候が発生するような樹木の配置を考えた事があったが、それを農業に利用しようとは・・・
挑戦してみる価値ありだと思った。
建築の世界でも、まさに農業のトレーサビリティーやフードマイレージの様な事が考えだされ、環境に負荷をかけない建築が求められているようだ!
農業の場合は「自分の健康のためにどのような食べ物なのか?」が求められていると思うが、建築の場合はもっと崇高なレベルで考えられているように思う。それゆえ、その事を本当に必要と感じる人がどれくらいいるのか?
自分の家の木材がどこの山で採れて、どのような経路でここに来たのか、それを理解する事で何が得られるのか?確かに輸送距離は環境に負荷をかけるから近い方が良いと思うが・・・
しかし、今後は間違えなくこの方向に向かうだろう。
この建築の視点から農業を語れたら、もっと深い意味を持つであろう。
「自然エネルギー」って本当は農業なんだと思う。どんなに技術が進んだとしても、太陽のエネルギーを動物のエネルギー(食べ物)に変換できるのは植物しか無いはず。
その意味では本当のソーラパネルは農地であり、一番人間に必要なエネルギー変換装置なのではないか?
建築の話を聞きに行ったのに、思いのほか農業の事を考えさせられた一日であった。
2010年4月
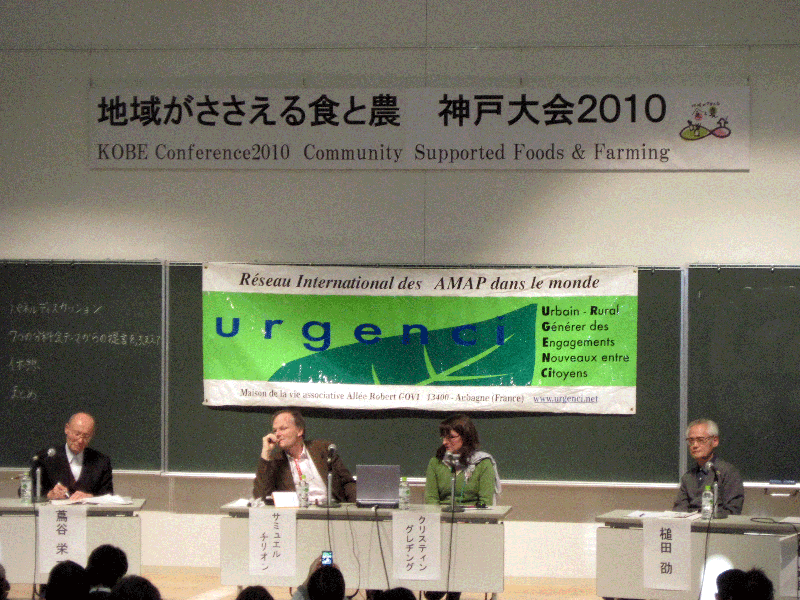 ■TEIKEI ■TEIKEI
先日神戸で行われた「地域がささえる食と農」に参加して来た。
消産提携運動がフランスで盛んになり国際団体URGENCI(ウージャンシー)が設立された。
国際大会をフランス、ポルトガル、フランスと開かれ、提携運動発祥の地「日本」での開催を海外の方が要望し神戸で開かれたらしい。
世界の有機農業は日本より進んでいるのかもしれない。
IFOAM、CSA,AMAP等、様々な団体、活動が行われているようで、おどろきの時間を過ごした。
アメリカの活動、オーストラリアの活動、フランス、カナダ、インドでは読み書きができない人に行われている「有機農業の認証」の話・・・
今、自分がどこに居て、何をしたいのか分からなくなるくらい刺激的な話ばかりだった。
北海道からも3人(エコビレッジでお世話になっている人も)の知人に会ったが、もっと多くの人に聞いて欲しい集まりだと思った。
普段、私も「農家さんの作った作物は芸術の作品と同じ」と話していたが、まさに同じ事を話す農家さんが居た。
「しかし、奈良さん、本当の芸術作品は心に響く物なんだよ、心に響く程のおいしい作物を作って始めて芸術作品になるんだ!」と言われ、頭を打ち抜かれた気分だった。
ある消費者の方は「生命のある物を売買する事は基本的に禁止されているはず、野菜だって生命があるのよ!私は農産物を商品とは思っていない、命のある物に消費者が価格をつけるなんてとんでもない、生産者が価格を決めるべき。」と話されていた。
スーパー等で「顔の見える関係」と最近写真付きの野菜が売られているが、ある農家さんは、「消費者は生産者の顔が分かるかもしれないけど、私たち生産者は消費者の顔が分からない、こんなの「顔の見える関係」って言えますか?有機農業は生産者と消費者が有機的に繋がるから有機農業なんだよ!
繋がらなくてはならないのは「心」なんだよ!と話されていた。
今、その言葉を思い出しても話をした人の熱意がリアルに思い出される。
以前、神戸の震災で丹波の農家が被災者へ「おにぎり」を届けた話を聞いた事があり、まさに今回この会場におにぎりを届けた人とおにぎりを受け取った人が居た。
3人で話す機会が出来、ただただ私は涙する事しか出来なかった。
震災の前から農業者と消費者が繋がっていて、「台風でニワトリ小屋が倒壊した時に消費者が神戸から来て助けてくれた。だから私は助けてもらった消費者を助けに行きたいと思ったんだ!」
両方とも助けてもらった時の感謝の気持ちは、私が想像できる領域ではないだろう。
都市と農村の交流とか北海道でも行われているが、本当の都市と農村の交流を見せてもらった。
二人とも良い笑顔で私に経験を話してくれた。
この二人に会えただけでも神戸に来たかいがあった。
第5回目の大会は韓国で行われる。
もっと「提携」(TEIKEI)が世界共通語として広まって行く事を願い、日本でも浸透して行く事を願いたい。
2010年3月
 ■作品「とちおとめ」 ■作品「とちおとめ」
先日本州で我が社のステビア資材を使ってくださっている農家さんを数件訪れた。
この写真はその時のイチゴ農家さんの作品だ。
3時間くらい箱詰め作業の間、色々お話を伺っていたが、1時間に1人くらいのペースで直接お客さんが買いに来るのだ。
別に「直売しています」なんて看板があるわけでもなく、リピーターになったお客さん達だ。
私も食べさせていただいたが、とてもおいしかった!糖度は18度あった。お土産に買って帰りたかったが、注文が来ているのを出荷するだけで精一杯で、奈良さんに渡すのは落ち着いてからにしてくれと言われた。
当社のステビア資材を使っていてこのように言われるのは、私に取って誇りに思えた。
まさにこの農家さんが作られているのは「作品」だと思った。
私はよく農家さんの農作物の事を陶芸家の作品のように準えて話する事がよくあるが、(江別がやきものの街であるが故)今回は逆に教わった。
「やきものは、土をいじって形を作って、釜に入れ、釜からどのような仕上がりになって出て来るか分からない。農業も土を作って苗を植えて実が出来るまでどのように出来て来るか何年やっていても分からない!確かに同じかもな!」
農家は毎年挑戦なんだよ!その基本は「土づくり」何だよ!と言われた。
農家さんの言葉はとても重く心に響き、その農家さんに我が社の「ステビア資材」を認めていただいたのは本当に誇りに思えた。
これからも「土づくり」に貢献できる会社でなければならないと感じた。
2010年2月
 ■耕盤層 ■耕盤層
秋に知り合いの農家さんから水はけの悪い畑があるから見てくれと言われ出向いた
畑に4カ所穴を掘り調査した。
暗渠排水は問題なかった。
おそらく耕盤層が形成されているのだろうと思った。やはりそうだ、写真の中央部に小さな穴があるのが分かると思うが、ピンで土を上から順番に刺していくと途中から硬い所が出てくる。
そこの土質だけが砂質系で締まりやすいんだろう。
農家さんはきめ細かにサブソイラーをかけているようだが、この土質は難しいと思う。
まさにこのような土質は有材心破工法が有効なんだと思う。
春の雪解けにもう一度伺う事にした。
2010年1月
|
