|
カバーコラム
毎月「暗渠」「ステビア」「農業」「農村景観」をテーマにカバーコラムを書いて行きます。
■土壌という字の意味
「土」という字と「壌」という字、「土」の字は象形文字で、下の「一」は大地を表し、その大地から芽が出て、葉が伸びて植物が生長する培地です。それが「土」の字の原形になっているようです。
「壌」という字は二つの意味があると思います。
一つ目は、「肥えたふくよかな」やわらかいイメージの意味です。
「壌」の土編が女偏になると「嬢」であり、柔らかなイメージになります。
二つ目は、「壌」の土編が酒偏になると「醸」、「かもす」の意味です。
時間をかけてかもし出すのが、醸造です。
微生物(乳酸菌、酵母菌、納豆菌、光合成細菌)の働きでゆっくりと澱粉が糖になってアルコールに変わってお酒になります。
「土壌」とは、やわらかく、肥えた場所で時間をかけてゆっくりと生長させる大地なのです。
2011年12月
■東北農業!
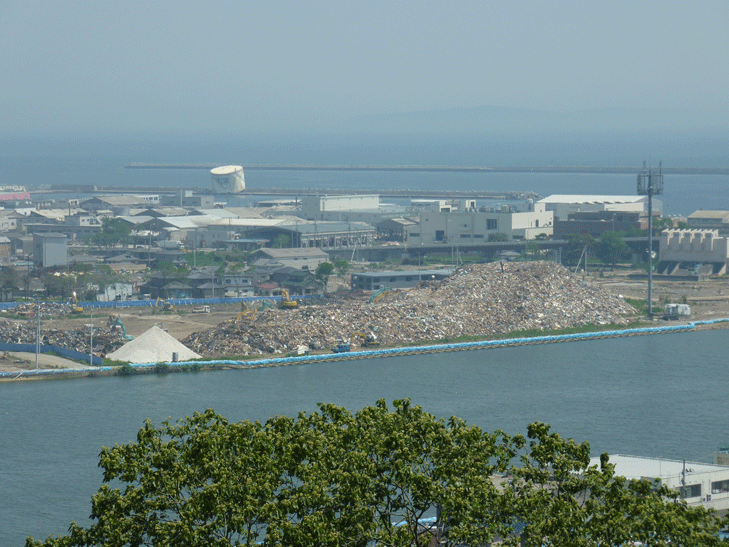 先週、石川県、滋賀県と打合せに行って来た。 先週、石川県、滋賀県と打合せに行って来た。
直接北海道に戻らないで、能登半島沖地震で石川県で対応した「瓦礫処理と暗渠排水」の話を聞いて欲しく東北を訪れた。
カバーコラムでも書いたが、石川県では屋根瓦を疎水材に利用している。今回の震災でも多くの瓦があるはずと思い歩いた。
東北は疎水材に「もみがら」を利用している地域なので、「瓦」利用はおもしろい発想と言われたが、除塩対策で暗渠排水を整備する事はないと言われた。
瓦礫の割合では「瓦」は少なく、その前に「木材」「コンクリート」「家電」と多くの山があった。
仙台で宿泊がとれず、鳴子温泉の湯治宿に泊まった。被災して来た人が居た。
夜に子供達と花火をし、私たちは日本の将来の子供達の為に何が出来るのか、考えさせられた。
2011年7月
■赤い根!
 今年は巴農場の田んぼでステビア米を作ってもらっている。ここの田んぼで出来たお米は全量ナラ工業で買い取ります。韓国はFTAに伴い企業が農家を支援する仕組みが出来ているらしい。昨年神戸で聞いた「URGENCI」の取り組みを少しでも我が社でもやってみたいと思っていた。 今年は巴農場の田んぼでステビア米を作ってもらっている。ここの田んぼで出来たお米は全量ナラ工業で買い取ります。韓国はFTAに伴い企業が農家を支援する仕組みが出来ているらしい。昨年神戸で聞いた「URGENCI」の取り組みを少しでも我が社でもやってみたいと思っていた。
写真は右側がステビア液を利用して育てた苗の根、左側は慣行栽培。
慣行の方が少し赤みが強いようにも感じるが、色の大きな差はない、原因は土質条件による物だろう。
田んぼに入るとアブクが発生する。ちなみにこのアブクにライターの火を近づけると、「ボッ!」って音がする。
メタンガスだ!田んぼが嫌気状態になっているからだ!
今年の春は雨が多く田んぼが乾ききる事無く農作業が始まったからであろう。今は暗渠排水を開放し、縦浸透が起きるようにして対策している。
写真では解りづらいが、右の根の方が根の先端にまで「ひげ根」が多いように思う。サンプル数が少ないから確実な差とは言えないが、以前、宮城の農家さんに聞いた。「育苗段階でどれだけ根を出せるかが問題」と言われていたので、ステビアで「ひげ根」を多く出す事に挑戦したので、たぶんうまく行っているだろう。
収穫時にどうなるか楽しみだ。
収穫までの状況をアップして行きたい。
2011年6月
■記憶とランドスケープ
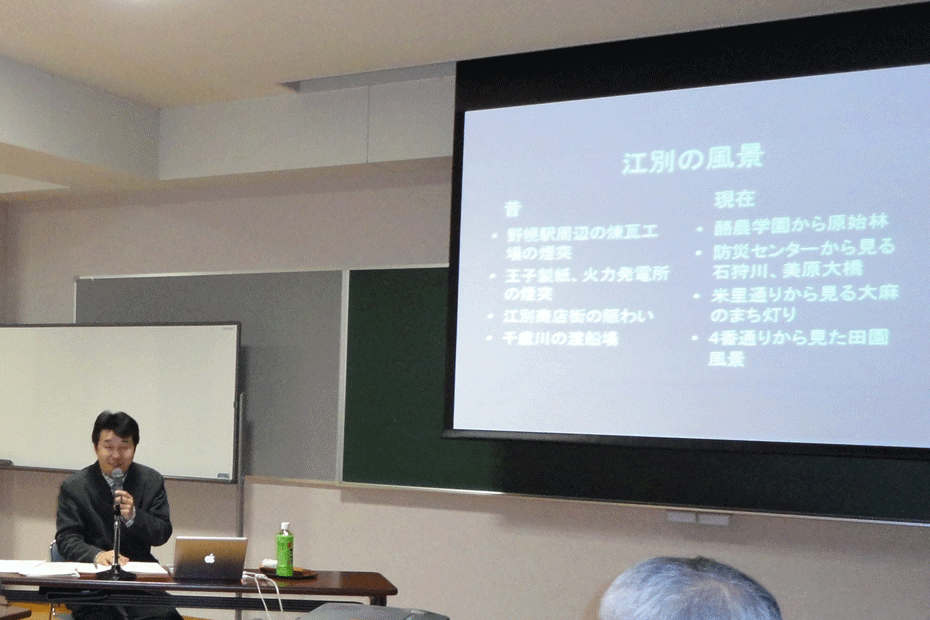 1月、2月と地元の生涯学習で講義をさせていただいた。テーマは「記憶とランドスケープ」 1月、2月と地元の生涯学習で講義をさせていただいた。テーマは「記憶とランドスケープ」
出張に行って朝、目が覚めた時「ここどこ?」って一瞬思う事がある。きっと多くの人が経験した事だろうと思う。自分の地理的位置を記憶しているから、部屋が普段と違うと一瞬ホテルにいる事を忘れてしまう。
昔住んでいた所を訪れると、昔の自分を思い出す。それが懐かしさだと思う。
自分の位置が歴史的にも確認するのが記憶だと思う。
物理的にも歴史的にもランドスケープを記憶し、自分が今、何処にいるのかを確かめている。
20世紀後半やたらと、歴史的建造物を残す活動が、日本全体で起きた。これは経済的に不安定な時代に、「自分たちの生きて来た証を残したい!」「先の見えない21世紀への羅針盤としたい!」と思って行われた行為だと思う。
自分の位置を確かめる為にだ!
設計事務所時代に建築家が「施設で生活しているお年寄りが痴ホウにならない為には、汚くても壊れていても良いから、元気だった頃の服や家具を施設に持ち込む事」と話していた。まさに同じ行為だと思う。
我が社に手伝いに来てくれているスタッフで「介護タクシー」を運転している人がいる。
以前、おばあちゃんを歌志内まで家族と連れて行って、故郷に近づくとベットに横になったまま乗っていたおばあちゃんが、身を乗り出して窓から外を見て泣き出した。と言う話を聞いた。このスタッフも「単なる自宅と病院を往復するタクシーではなく、感動を与えるタクシーにしたい!」と言い、私も「あなたのした行為は、物理的に距離を運んだタクシーではなく、おばあちゃんにとってはタイムマシンの様なタクシーで昔の記憶まで運んであげたんじゃない」って事を話した。
今回の東北の震災、東電の事故の事を思うと、避難している人たちは、記憶とランドスケープが断ち切られたのだと思う。
未来に向かって歩き出すには相当の強い気持ちが必要だろう。北海道の開拓時代の精神ように立ち向かって欲しい!
2011年5月
■神野(カミノ)
 東日本震災で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。 東日本震災で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
3月11日東北地方で大きな地震があった。私の友人も震災にあい、北海道から持ち込んでいた、ジャガイモ、お米を送った。
日本がこの震災で何を学ばなくてはならないのか?今、自分は普通に仕事をしていていいのか?被災地に駆けつけなくてはならないのではないか?
2月のカバーコラムに書いた農家さんは宮城の人だし、宮城は農業国でもあるし、落ち着かない日々が続いた。
しかし、能登半島の地元の農家さんは期待してくれている。そう思うと私の役目は、この条件の悪い田んぼを改良し、来年、一俵でもお米を穫ってくれれば、東北の人にも届くだろう!だから私の被災者支援活動はこの農地を良くする事だと言い聞かせ、現場を叩いた。
宮城の農地は海水をかぶり間違いなく「塩害状態」であろう、液状化した地域も同様であろう。そう考えると私たちの技術「暗渠排水」が必要なのは火を見るより明らかだ。
会社の体制を整え、東北の地域にも私たちの技術が届くようにがんばろう!
来年の食料を生産できるよう我が社も努力しよう!
こんな事を考えられさせた工事の地域が、「田の神様」をまつる風習のある地域「神野」であった事も神様から「ナラ工業の使命を考えろ」と言われたような気がした。
2011年4月
■稲塚権次郎
 みなさんは稲塚権次郎という方をご存知であろうか? みなさんは稲塚権次郎という方をご存知であろうか?
私は「この人が今の世界の食糧の基礎を作った」と言っても過言では無いと思う。
富山県の城端町出身で昭和10年に岩手県で「小麦農林10号」を開発した。
この小麦は終戦時にGHQによりアメリカに渡り、ボーローグ博士らにより改良され、世界中で植えられ、世界の食糧危機を救ったと言われている。
この事は「緑の革命」と呼ばれ、ボーローグ博士は後にノーベル平和賞を受賞している。
我が社が、現在北陸で仕事をしているのも、実はこの稲塚権次郎さんのおかげだ。
稲塚権次郎が一線を退職し、地元で土地改良事業の役員をしている頃に、我が社の社長が呼ばれ(30代の頃)、トレンチャーや暗渠排水の必要性を説いたようだ。
「北陸の裏作で麦を作らないと日本は駄目になるぞ!その為には暗渠排水が必要だ!トレンチャーを用意すれ!」と
社長は「風貌の変わった勢いのある変なおじさんだな」というのが印象だったようだ。
後にあのおじさんがそんなすごい人だと驚いたらしい。
TPPで大量の小麦が日本に入ってくる事は、稲塚権次郎さんの教え子達が帰ってくるような事かもしれない。
「水稲132号」も開発し、東北の飢餓を救う為に、宮沢賢治がこの米を広め、尊敬されるようになったのも、稲塚権次郎さんがきっかけだ!
後にこの米がコシヒカリ、ササニシキを生み出して行く。
今の日本を見て稲塚権次郎さんは何と思うだろう?
今年はお米の生産量を800万tを切る!小麦の自給率は14%!
裏作で作る小麦は売り物にならないと言われている。
こんなに日本の農業に貢献した人がいる。この強い意志を私たちは引き継がなくてはならない!
私も「変なおじさん」と思われようと、「正しい事は正しい」「必要な物は必要」と訴えて行こう!
2011年3月
■稲の根
 先日、宮城県で我が社のステビアを利用していただいてる農家で集まりがあり、参加して来ました。 先日、宮城県で我が社のステビアを利用していただいてる農家で集まりがあり、参加して来ました。
北は北海道、南は長崎まで総勢20名。
この農家さんの知合いばかりで、実は現地に着いて、北海道の我が社のお客さんの農家さんと出会い、「意識が近い人は寄るもんだんな」とお互い驚いていました。
実はこの農家さんは今年「ステビアグリーンパワー」を散布したほ場が、コシヒカリ、反収13俵で全て一等米との事で、お世話になっている人、この人の農業を手本にしている人を集めて意見交換会を開いたのです。
写真はその農家さんのお米の根の写真です。
暗渠排水を専門としている立場から、この根を見て、おそらく酸素条件の良い田んぼなんだと思いました。その条件のあるほ場にステビアを撒いたのでより効果が現れたのだと思います。
根が酸欠をおこしていない、白い根です。左側に二本に関しては、白いだけでなく、根がとても細いです。根が細いって事は、栄養の吸収性も良いので、それだけの収量を上げたんだと思います。
我が社の願いは、日本の農家さんのほ場を改善し、吸収性の良い土壌環境にするのが目的だと考えると、この根は一つの解答を示してくれたと思います。
2011年2月
■TPP
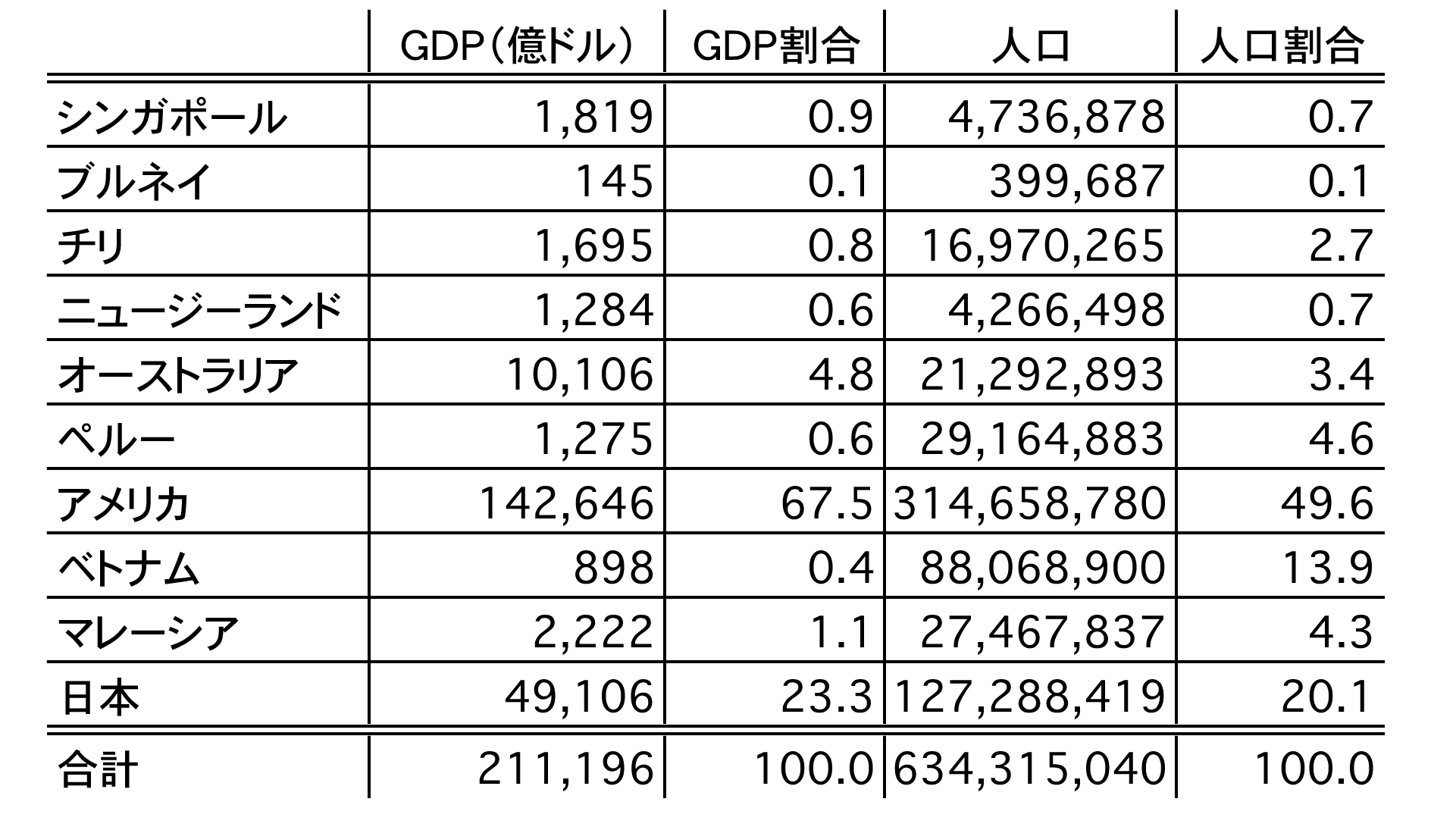 正月休みに大学で講義する内容の整理をしていた。久しぶりに机に向かって物を考える事をしていたので、思考が拡大し、TPPの事を少し調べた。 正月休みに大学で講義する内容の整理をしていた。久しぶりに机に向かって物を考える事をしていたので、思考が拡大し、TPPの事を少し調べた。
会社のHPという性格上TPPの話をするのは好ましくないが、あえて自分の考えを述べる事にする。
農業に関わる仕事をしているが個人的には、農業を強くする為には必要な物と考えていた。正確に言うとTPPが有ろうが無かろうが「農業を強くする」って事はやっていかなくてはならない!
農業者が安にTPPを反対しているような報道も多いが、それではなぜTPPを行うのか?
経済界は「これに参加しないと世界から残される」とか「輸出を強くして日本の景気を回復」等と言っているが、TPPに参加予定している国のGDPと人口を調べてみた。(表参照)
誰が日本の工業製品を買うの?
GDPではアメリカと日本で90%、人口でも70%。
市場の小さい所に輸出できるようになって日本の経済がかわるのですか?
これならアメリカと2国間で行うEPAかFPAを行うのと同じではないか?
日本国民が将来の日本をどのようにしたいのか真剣に考え、その議論の上で行動すべきだと思う。
ここ北海道は農業国であるため、反対の意見を聞くが、ただ単に「自分の身を守りたいから反対」と捉えられてしまいますので、大局的に見て説明し反対を唱える事をしなくては駄目だと思う。
どれだけの人がこのHPをご覧になっているかわからないが、考えるきっかけにしていただければ幸いだと思います。
2011年1月
|
