暗渠排水の歴史
~暗渠排水の歴史と江別~
農業の暗渠排水は古く江戸時代でも行われていましたが、その暗渠は竹や砕石を使ったもので土管は使われていませんでした。
西洋では暗渠排水土管を手で作っていましたが、世界に広がったきっかけは、1851年に行われたロンドン万博です。この万博はジエームスワットの蒸気機関などの産業革命として有名でしたが、実はこの万博に土管製造機が出品されており「農業の近代化の始まり」とも言われています。
日本で最初に「暗渠排水用土管」が作られたのは北海道だといわれています。 明治12年頃に札幌農学校のウイリアムブルックスによって土管製造機が輸入され、現在の北海道大学の北側の農場に施工されました。今でも北海道大学の第二農場に当時の土管が展示されています。
江別という地域は明治6年に榎本武揚が農場を開いたことにより始まりました。 明治11年に江別に屯田兵が入り、開拓使長官であった黒田清隆が開拓使顧問としてアメリカから招かれたクラーク博士とエドウィン・ダンにこの開拓農地で作物を作るにはどうしたら良いか相談していました。その時の回答が、 「・プラウをかける・輪作をしろ・瓦筒を埋めろ」でした。 100年以上経った今でも同じような農地管理を行っています。ここに出てくる「瓦筒」が土管の事です。ブルックスノートにも「tile drain」と書かれてあり、 当時「土管」という言葉がなかったので「瓦筒」と訳されたと考えられます。 エドウィン・ダンは役人であった為公文書が残っているそれを調べると明治14年「昨年、江別村で行った暗渠排水のその後の状況を心配している」という文献がありました。この事実から明治13年に江別で暗渠排水を行われたのが分かります。これが札幌農学校以外で行われた日本で初めての暗渠排水です。
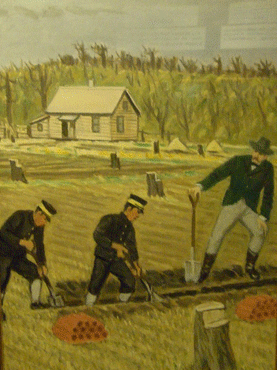
NORINTEN
”農の神”と呼ばれた男~稲塚権次郎物語~
- 世界の食糧危機を救った「小林農林10号」を育てた育種家 稲塚権次郎には苦難と挫折があった
- 最愛の妻 イトさんと母 ヨウコさんを見守った日々
- 今こそ「食のチカラ」が大切な時、権次郎が追い求めた思いを世界に発信する
2015年の秋に公開された、中代達矢さん主演の映画です。育種家として数々の稲と小麦を生み出し、育て上げた稲塚権次郎の物語です。江別で撮影が行われました。
ナラ工業が石川県で仕事をするきっかけとなった映画です。また、稲塚権次郎は江別の代表的な小麦「ハルユタカ」のおじいちゃんにあたる小麦を作った人物です。

